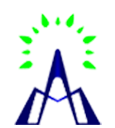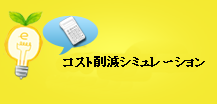内蔵電源直管LED蛍光灯は電気用品安全法(丸型PSE)に適合可否について
いよいよLEDが電気用品安全法(PSE法)の対象に入ってきました。
経産省は、PSE法の規制対象に、LEDランプ・LED電灯器具が追加されることを発表し、2012年7月1日から施行しました。
PSE法は、電気用品による危険や障害の発生を防止することを目的とした法律で、国が定める技術基準に適合し、その基準への適合を示す「PSEマーク」が表示されない製品は、国内では流通できないことになっています。
今回の改正では、定格消費電力が1W以上のLEDランプ、およびLED電灯器具(防爆型は除く)が、規制対象品目として追加され、LEDランプでは、口金が定格電圧が100~300Vかつ定格周波数が50/60Hz(ヘルツ)のものが対象となるため、現在、一般的に流通しているE17口金、E26口金などLED電球全般が該当することになります。
しかし、「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」では、「エル・イー・ディー・ランプ」を「定格消費電力が一ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。」としておりました。
平成23年7月6日の改正法の公表以来、多くの人が「一の口金」について悩んだことでしょう。
片側給電の直管形LEDランプを製造、輸入する私たちも、この点にずいぶん振り回されています。
「一の口金」については、今も混乱が続いております。
直管形のLEDランプは(電源内蔵)、今回の改正の対象なのか、それとも今後も非対象なのかといった疑問です。
両端に口金が付いた直管形。
これは、「一の口金」ではありませんから、明らかに本改正の非対象LEDです。
では、両端に口金がついた直管形LEDランプのうち(電源内蔵)、片側給電タイプはどう考えればよいのでしょうか?
見た目には、二つ口金がついていますよね。けれども給電は片側のみで、つまり、二つのうち、一つの口金(G13)は機械的に接続する目的のみで使用されています。
「電気的接続が可能かどうか?」というところで「口金」か否かということが決定するのであれば、やはり片側給電タイプは二つの口金を有し、非対象という考えになるのでしょう。
技術基準(案)の中にはG13口金に関する規定がありませんので、G13口金を有するものは電気用品ではないので、技術基準に想定する必要がないということです。
今一般的に出回っている両側給電タイプの直管形LEDランプは、一の口金ではありませんから、省令改正後もこれまでどおり「対象外」という扱いになります。
しかし、「LEDがPSE対象になったけど、どうしておたくのにはPSEマークがついてないの?」
いくら説明しても、買う側の人は理解してくれないことも少なくありません。
世の中にはPSEマークを三種の神器のごとく、「対象/非対象」に関わらず、崇め奉る人がいます。
安全性が先か、マークが先か?
「ほしいのは、そのマークか?」というお話になるわけです
一部に、無理やり「対象」になるような構造にして、PSEマークを表示したい人もいます。