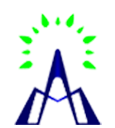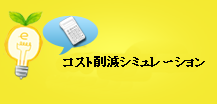ノーベル物理学賞に赤崎・天野・中村氏 青色LED発明
ノーベル物理学賞に赤崎・天野・中村氏 青色LED発明
【パリ=竹内康雄】スウェーデン王立科学アカデミーは7日、2014年のノーベル物理学賞を赤崎勇・名城大学教授(85)、天野浩・名古屋大学教授(54)、中村修二・米カリフォルニア大学教授(60)に授与すると発表した。少ない電力で明るく青色に光る発光ダイオード(LED)の発明と実用化に貢献した業績が認められた。照明やディスプレーなどに広く使われている。世界の人々の生活を変え、新しい産業創出につながったことが高く評価された。
日本のノーベル賞受賞は12年の生理学・医学賞の山中伸弥・京都大教授から2年ぶり。計22人となる。物理学賞は素粒子研究の08年の南部陽一郎(米国籍)、小林誠、益川敏英の3氏以来で計10人となった。日本の物理学の高い実力を示した。
授賞理由は「明るくエネルギー消費の少ない白色光源を可能にした高効率な青色LEDの発明」で、「20世紀は白熱灯が照らし、21世紀はLEDが照らす」と説明した。
LEDは1960年代に赤色が開発された。緑色も実現したが、青色は開発が遅れた。あらゆる色の光を作り出せる「光の3原色」がそろわず、「20世紀中の実現は不可能」とまでいわれていた。
その壁を破ったのが赤崎氏と天野氏だ。品質のよい青色LEDの材料を作るのが難しく、国内外の企業が取り組んでもうまくいかなかった。両氏は「窒化ガリウム」という材料を使い、明るい青色を放つのに成功した。
中村氏はこれらの成果を発展させ、安定して長期間光を出す青色LEDの材料開発に乗り出し、素子を作製した。量産化に道を開き、当時在籍していた日亜化学工業(徳島県阿南市)が93年に青色LEDを製品化した。
赤崎氏は7日の記者会見で「半分サプライズで、こんな名誉なことはない」と語った。中村氏は同日、大学構内で記者団に対し「ノーベル賞は基礎理論での受賞 が多い。実用化で受賞できてうれしい」と語った。天野氏については「海外出張中で、帰国後記者会見する」と名大側は説明した。
日本の強み である材料技術がLEDの光の3原色をそろえることに貢献し、LEDによるフルカラー表示が可能になった。電気を直接光に変えるLEDはエネルギー損失が 少ない。素子そのものが光るので電子機器の小型・軽量化に役立つ。薄くて省エネのディスプレーなどデジタル時代の幕開けにつながった。
3原色を混ぜ、自然光に近い白色光も再現できるようになった。省エネ照明として家庭にも浸透し始めている。現在、産業社会で消費するエネルギーの20~30%は白熱灯や蛍光灯などの照明が占めるといわれ、これらがLED照明に置き換われば、地球温暖化を防ぐ切り札のひとつになる。
青色の光は波長が短く、デジタルデータの書き込みに使えば大容量化できる。中村氏は青色LEDの後に青色レーザーの基盤技術を開発した。ブルーレイ・ディスクのデータの書き込みに青色レーザーが使われているように、大容量の光ディスク実現につながった。
授賞式は12月10日にストックホルムで開く。賞金800万クローナ(約1億2000万円)は3氏で分ける。