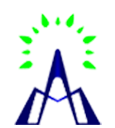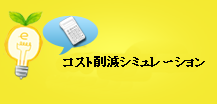約75万m2を照らす大型LED照明【PR】
集光性とワイドな照射範囲の両方を実現するLED
コンテナ埠頭ターミナルや荷役機器の管理・運営を行う名古屋ユナイテッドコンテナターミナル株式会社。中部圏の国際貿易港として発展してきた同社は2015年12月、名古屋港鍋田ふ頭において国内コンテナターミナルとしては初となるヤード全域の照明LED化に踏み切った。約75万m2という広大な敷地に広がる高さ40mの照明塔。そこに計177灯の大型LEDが導入された。
数年前から荷役機器の電動化やハイブリッド化をはじめ、省エネ活動を推進してきた同社だが、照明のLED化に関しては、求めている仕様条件を満たす製品と出会うことができず、またイニシャルコストが高いこともあって導入は足踏み状態となっていた。
「LEDは集光性が高いため、遠方かつ広範囲を照らしたいという当社の要望を満たす製品がなかなか見つからず、その間は照明の間引きなどにより節電を図っていました」と取締役兼業務部長兼鍋田ターミナル所長の北地幸二氏。
前述のような厳しい仕様条件を満たす製品として選ばれたのが、ニイヌマ株式会社のLED照明「クレア」である。
今回は投光器型の大型LED2000~4000(水銀灯比2000~4000W相当)が採用された。同製品の一番の特徴は1つの照明器具にユニットが2~4つ付いており、ユニットごとに角度の微調整が可能だということ。光源の典型的な特性として、光の照射距離を伸ばそうとすると照射範囲が狭くなる。この条件において広範囲を照らそうとすると、照明の台数が必然的に増えてしまうのだ。
しかし、「クレア」の場合はユニットの角度を調整することで配光範囲を広げることができる。1ユニットの配光角が15oであったとしても、ユニットが4つ付いていれば、その角度調整によって1つの照明で60oの配光角、もしくは設置する高さによってはそれ以上の値が期待できるということだ。
まさに、「遠くに光を飛ばすかつ配光角度も広げる」というニーズを実現した製品だといえる。
照明の消費電力を50%以上も削減
「1灯で水銀灯1000W投光器の2~4灯の役割を果たす同製品の導入を決めたことで、元々306灯あった照明の数を半数近くの177灯まで減らすことができました」と伊藤氏。
照明灯数を減らしながらも照度は保つことで作業性に問題はなく、さらには消費電力50%以上の削減に成功した。導入においては、環境共創イニシアチブ(SII)のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金を利用。4年弱でイニシャルコストを償却する見込みだ。
LED照明の設置場所が屋外ヤード・沿岸部ということもあり、防水機能に加えて、耐塩対策も求められた。この点に関して、ニイヌマは表面をアルマイト処理した標準仕様にさらにポリエステル系粉体塗料を焼付塗装した重耐塩塗装を提案。そのほか、雷対策としてサージプロテクタも取付けた。
「鉄塔やガントリークレーンなど高い建物や機器があるため避雷針を設置していますが、これは雷の電流を地面へ流すためのものであり、機械に関しては別の対策を施さなければ壊れてしまいます。LEDも電子機器ですから、サージプロテクタの設置は外せない必要仕様条件の一つでした」と北地氏は説明する。
24時間365日稼働しているコンテナターミナルでは、故障時の対応の良さもLEDメーカーを選定するうえでの重要な要素であった。故障の連絡が入ったら即座に現状復帰を行ったうえで原因を調査するというニイヌマの迅速で丁寧かつ的確な対応が、同社製品の導入を促進する一手となったといっても過言ではない。
同業他社に先駆けてヤード全域の照明LED化を実現した名古屋ユナイテッドコンテナターミナル。省エネの次なるステップとしては、消費エネルギーにおいて大きな割合を占める電力使用量を抑えるため、一時的に発生するピーク電力の削減を目指す。
「まだ構想段階ではあるが、機器設備を時間差で稼働することで使用量を制御する、蓄電池を活用するなどしてピーク電力を抑えていきたい」と伊藤氏はその展望を語る。
コンテナターミナルという広大な敷地において、ヤード照明の完全LED化を実現した名古屋ユナイテッドコンテナターミナル。
「遠方を明るく照らす集光性」と「近くを広く照らすワイドな照射範囲」、これら両方の特性を備えたLED照明を探し求めていた同社は、複数のユニットの角度調整によって照射範囲の拡大を可能にするニイヌマの大型LED照明を導入し、消費電力50%以上の削減を実現した。